2014年、Twitterでは「ドラゲナイ」という謎のワードが突如として話題になりました。
SEKAI NO OWARIの楽曲「Dragon Night」のタイトルが空耳的に「ドラゲナイ」と聞こえることから、 SNS上で爆発的に拡散。歌詞の内容とは関係なく、このフレーズがネタとして独り歩きしました。
では、実際にどのくらい流行っていたのか?最近の「猫ミーム」などと比べるとどれほどの影響力があったのか? 当時のTwitterの様子を振り返りながら検証していきます。
- 「ドラゲナイ」現象は2014年にTwitterを中心に爆発的に拡散
- 大喜利ネタや合唱コンクールでの採用など、多方面で話題に
- 流行の持続性は短期的で、「猫ミーム」ほど長くは続かなかった
- SEKAI NO OWARIのメンバーも流行を受け入れ、ライブなどで活用
「ドラゲナイ」とは?なぜTwitterで流行したのか
2014年、SEKAI NO OWARIがリリースした楽曲「Dragon Night」は、音楽業界のみならずSNS上でも大きな話題となりました。
特に、楽曲のタイトルが空耳的に「ドラゲナイ」と聞こえることがTwitterでネタ化し、
といった形で拡散され、Twitterのトレンドワードに入るほどの盛り上がりを見せました。
さらに、楽曲のリズミカルなメロディーと独特の雰囲気が「合唱コンクール」や「文化祭」でも広く採用されるようになり、若者を中心に浸透しました。
「猫ミーム」と比べた影響力と持続性
では、「ドラゲナイ」現象は最近のネット文化の象徴である「猫ミーム」と比較するとどのような位置づけになるのでしょうか。
共通点
- Twitterを中心に爆発的に広がった
- 大喜利的な使われ方で、SNSの文化と親和性が高い
- 拡散される理由がシンプルで、特定のファン層以外にも届いた
違い
- 「猫ミーム」は画像主体で派生が多く、長期間愛される傾向がある
- 「ドラゲナイ」はフレーズ主体で、短期的に消費されやすい
- 「猫ミーム」は現在も頻繁に新作が生まれるが、「ドラゲナイ」は特定の時期に流行したのみ
つまり、「ドラゲナイ」は2014年のTwitterトレンドを象徴する一過性のブームであり、「猫ミーム」のような長寿命のネット文化とは異なる性質を持っていました。
「ドラゲナイ」ブームを受けたメンバーの反応

SEKAI NO OWARIのメンバー自身も「ドラゲナイ」現象を認識しており、ライブやインタビューで言及することがありました。
Fukaseさん
「『ドラゲナイ』って呼ばれるのは正直最初は面白かったけど、こんなに広がるとは思わなかったね。」
Nakajinさん
「リビングにターンテーブルを置いてDJの気持ちになって作った曲が、こんな形で広まるとは(笑)」
Saoriさん
「歌詞の世界観が好きなんだけど、ネタとして使われること自体はポジティブに捉えてるよ。」
メンバーはこの流行を否定することなく、むしろポジティブに捉えていたようです。
「ドラゲナイ」現象の過去の類似事例
Twitterで短期間に爆発的に流行し、その後沈静化したネットミームには、過去にもいくつかの例があります。
①「ぽぽぽぽーん」(2011年)
東日本大震災後のACジャパンCM「あいさつの魔法。」の「ぽぽぽぽーん」がネットミーム化。ドラゲナイと同様に一発ネタ的な流行。
②「倍返しだ!」(2013年)
ドラマ『半沢直樹』の決めゼリフが社会現象化。Twitterでの拡散力は強かったが、持続性がやや短い。
③「ンゴwww」(2014年)
2ちゃんねる発のネットスラングがTwitterでも広まり、若者の間で定着。
これらの事例と比較しても、「ドラゲナイ」は短期的なブームとしての側面が強く、広がり方としては「ぽぽぽぽーん」に近い形であったと考えられます。
まとめ:「ドラゲナイ」は短期的な大流行だった
結論として、「ドラゲナイ」は2014年のTwitterで確かに大流行しましたが、その影響は一過性で、猫ミームほど長続きするものではありませんでした。
- Twitterの大喜利文化と親和性が高く、一気に拡散された
- 文化祭や合唱コンクールなど、リアルな場にも影響を与えた
- しかし、持続性は短く、「猫ミーム」のような長期的なネット文化とは異なる
- メンバー自身も流行を受け入れ、ライブやメディアで活用していた
10年前のTwitter文化を振り返る上で、「ドラゲナイ」は確かに象徴的な現象だったと言えるでしょう。

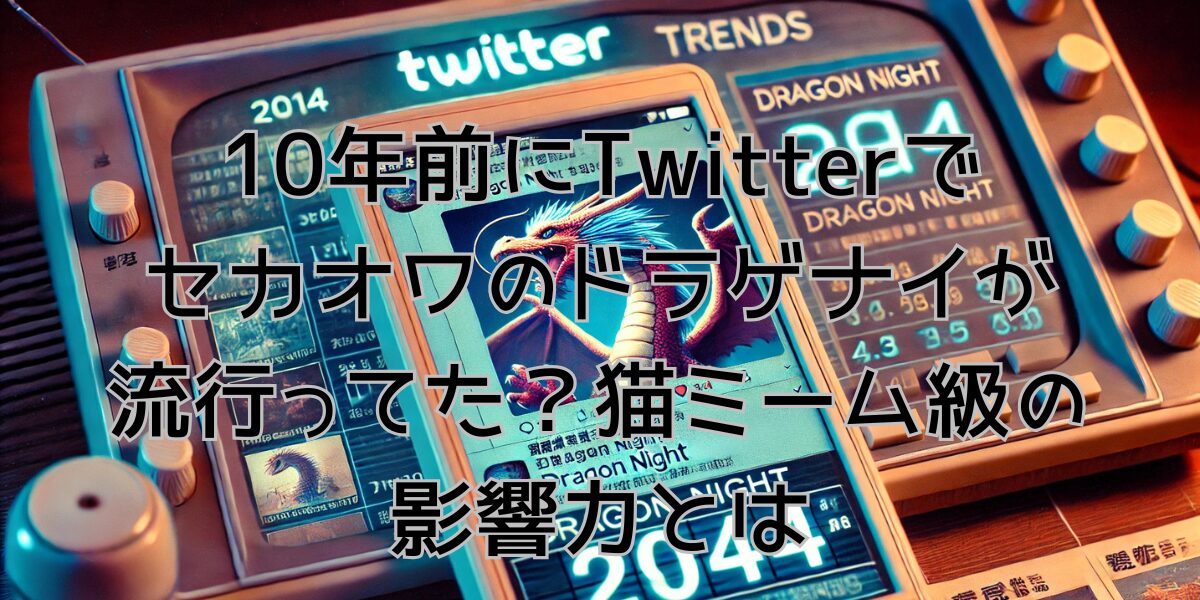
コメント